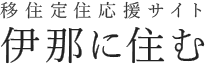伊那谷の仕事と暮らしvol.1 タカノ株式会社
ページID:592196565
更新日:2020年9月18日
「挑戦」というキーワードで仕事もプライベートも前向きな暮らし
伊那市西春近、天竜川沿いの道を通ると目に入るのが、大きく「KOKUYO」と書かれた倉庫。小さなころからこの地に住む私たちにとっては、見慣れた景色ですが、大人になって気づくこと。「伊那市にはKOKUYOの会社も工場もないよね…?」。その答えが、今回インタビューに伺ったタカノ株式会社さんにあります。

「製造業」という仕事の多様性
「創業はばねの製造から始まっていますが、今ではオフィス家具、エクステリア、ヘルスケアなどさまざまな分野に展開しています。KOKUYOブランドのパイプ椅子をはじめ、様々なオフィスチェアを弊社で作っているんですよ」。会社についてお話しをしてくださったのは、人事部人事課の森田貴子さん。「KOKUYO」の大きな看板が伊那にあるのは、タカノさんでその多くを製造しているから。
製造業の多いこの伊那谷。多くの企業が高い技術力を持っているからこそ、大手企業のOEMやODM(注釈1)の生産を担っているのですが、それらは公にできないもの多く、私たちが知る機会がないことが、ほとんど。その中で、「KOKUYO」ブランドのイスがこの地で作られている、ということが知れるのは、川沿いに建つ大きな倉庫のおかげでもあるのです。
注釈1
OEM…委託者からの発注にしたがい製品を製造すること
ODM…製品の開発から製造を一貫して受託すること
そんな、パイプ椅子などの製品を作るための社内設備を設計する仕事を担っているのが、ファニチャー部門で生産技術を担当している伊藤慶彦さん。「大学では工学部の機械工学科を専攻していて、学んだ事が今の仕事に直結しています。子どものころに工場見学に来たことがあって、この会社にはなじみがありました。お客さんの近くにいる仕事ではないのですが、現場で使ってくれて、ありがとう、という言葉をもらえるととても嬉しいです」。一口に製造、モノづくりと言っても、それぞれが担う役割は多岐に渡ります。自分が考えた機構で製品が作られていく、そんなプロセスも製造業の面白さ。
さらに「製造業」というイメージだけで、業務の内容を想像しないでほしい、と話してくれたのは、ヘルスケア部門事業企画課の下澤沙織さん。福祉や介護、小児サポート器具などを扱う部門の経営事務や損益計算を担当しているそう。「メーカーで働くっていうとモノを作っているというイメージがありますが、それ以外の仕事もたくさんあります。私は経営情報学部を専攻していたので、今の仕事に活かされています。文理関わらず、女性も多い職場ですね」。製造業、というとそこで作られる製品のイメージにとらわれて、モノをつくる技術や知識を有していることが重要かと思ってしまいますが、少しお話しを聞くだけでもさまざまな役割によって会社が成り立っていることがわかります。
「挑戦」というキーワード
下澤さんは二人のお子さんを育てる母親でもあります。「祖父母が子どもの面倒をみてくれるから、とても助かっています」。とはいっても、子育てをしながら仕事をする、というのはとてもエネルギーのいること。にもかかわらず、さらに自ら取り組んでいることがあるそう。

夏の休日は流しそうめん

ひいおばあちゃんと縁側で一緒にパチリ
「ひとつ、独学で勉強していることがあって。ヘルスケア部門で小児障害児に関わっています。その中で、会社としてだけでなく、いち母親としても感じることがあって、もっと深く学びたいと思うようになりました。朝子供が起きる一時間前に起きて資格の勉強をしています。いずれはそれが会社のためになるのではないか、と思っていますが、歩みは遅いですね(笑)ゆるーくやっています」。
ともすると、日常に追い立てられて自分のための時間を作ることをおざなりにしてしまいそうですが、下澤さんの前向きさはどこから来ているのでしょうか。
すると森田さんからこんなお話しが。「社員の想いや、うちはこういうところがいいところ、こういう風にしていきたいねということを経営陣と社員が共に再構築したい、方向付けをしたいということで、経営理念を考えるプロジェクトを立ち上げて、役員に提案する機会を設けたんです。最終的に共有する価値観として、今まであった“誠実・創意・根性”にプラス“挑戦”というキーワードが加えられることになりました。社内をあげて挑戦する環境を推進しています」。
下澤さんの所属するヘルスケア部門では、”進化できるものだけが生き残れる”と部門長が折に触れておっしゃっているそう。「変化に対応できる挑戦の仕方を全員考えながらしようという雰囲気もあります。営業なんかは目に見えた目標値がありますが、事務部門だとなかなか成果があらわれにくい。そのぶん自分のスキルを磨こうとする人が多い気がしますね」。
なにかに挑戦しようとか、前向きに取り組んでいこうということは、ひとりだけのエネルギーでは難しいもの。会社で日々ともに過ごす人たちが、「挑戦」しようという思いを持っていることが、ひとりひとりの前向きな力に繋がっていると感じられるお話でした。
左 伊藤さん、 右 下澤さん
人事課の森田さん
地元で働き暮らすことの楽しみ
そんな下澤さんはプライベートでも早起き。早朝4時に起きて、お子さんとカブトムシを取りに行くこともあるそう。「休みの日は松川のほうにカブトムシを取りに行ったり。あるときは捕まえたカブトムシを保育園に持っていくつもりが、車に置いて行ってしまって。車の中に置きっぱなしにしてカブトムシが熱中症になったら困るって(笑)会社の机の下に避難させて、保育園に届けたこともありました」。カブトムシと一緒に出社とは、都会ではなかなか見られない光景かもしれません。いや、地方でもなかなかないかな(笑)。生活と仕事の距離の近さを感じるエピソードです。
カブトムシはさておき、伊那の地で働くことに、皆さんはどんなメリットを感じているのでしょうか。神奈川の大学に進学して都会生活を体験した伊藤さんが、地元に戻ってきたきっかけはなんだったのでしょうか?
「神奈川県の大学に通っていて、就職活動は都会と地元と両方でやりました。実際は内定をいただいたところで働くしかない、という気持ちでしたが、長男でもあるし、家族の近くである地元に帰りたいという思いが強かったです」。
気心知れた同級生もいる安心感と、生まれ育ったところに戻る責任感が戻ってくることの大きな理由の一つだったそう。とはいえ、神奈川のような都会と比べて、地方には”ないもの”も多くてつまらないことはないのでしょうか。
「学生の頃からブレイクダンスをやっていました。戻ってきてからひとりでやるのはいやだなと思っていましたが、体育館とかに行ってみたら仲間になれる人たちがいて。週1、2回、スタジオや体育館で練習をしています。地元のお祭りで披露する場もありますし、こちらは住み慣れた環境で生活に不便さは感じませんね」。
伊藤さんのブレイクダンスは地元のコンテストで優勝するほどの腕前なんだそう。地元に暮らす人と話していると、たまに「ここは何もないから」という人に出会うことがあります。地域を見るときに「なにもない」というフィルターを通してしまうと何も見えなくなるけど、好きなことを楽しもうというフィルターで見ると、楽しめる環境も仲間も見つかる。それが伊那の暮らしなんだと感じます。
趣味のダンスはコンテストで優勝するほど
コロナ禍というタイミングとこれから
今、誰もが予想していなかった新型コロナウィルスによって、社会が大きく変わっています。人事を担当する立場として、森田さんにお話いただきました。
「東京で創業した弊社が、戦争の時代に疎開してきたことがこの地に根付いたきっかけです。縁もゆかりもない企業をこの地の皆さんが受け入れてくれたことに、地域があってこその会社だという社長の想いがあります」。
コロナ禍ではファニチャーやエクステリアのミシンのラインでマスクを縫って自治体に寄贈したり、大阪大学主体のプロジェクトへ参加し、フェイスシールドのフレームを3Dプリンタで作って無償で提供したりするなど、社会貢献も大切にしているそうです。
社会の変化によって、都会に暮らす人の価値観や地元を出て進学した学生の就職観に変化を感じることはあるのでしょうか。
「とくに最近では新型コロナウィルス感染拡大の影響などからIターン、Uターン希望の学生や転職者が多くなっているように感じますし、将来的に戻ることを希望する学生も増えてくるという気はしています。だからこそ、地元で働く場所を提供していくことが大事だと思います」。
「上伊那はほかの市町村に比べて、連携してやっていこう、この地域で盛り上げていこう、というムードが強い気がします。それが上伊那の人柄の良さなのかと最近思いますね」。
ピンチをチャンスに、ではないけれど、起こってしまったことを悲観するのではなく、その中からできることを見出していく。これから地元に戻ってくる人や移住を検討する人が増えていく可能性があるなら、地域をあげてここでの楽しい暮らしや仕事を伝えていきたい。そんな前向きな気持ちが共有できたインタビューでした。
左:下澤沙織さん、中央:伊藤慶彦さん、右:森田貴子さん
タカノ株式会社についてはこちらから
伊那谷で働くみなさんの「仕事」と「暮らし」を紹介します
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 地域創造課 移住定住促進係
電話:0265-78-4111(内線2251 2253)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:jkz@inacity.jp