
| 目 次 | 第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章 |
第5章 |
第6章 | 第7章 | 第8章 | top | ||
| 第5章 新市の施策 |
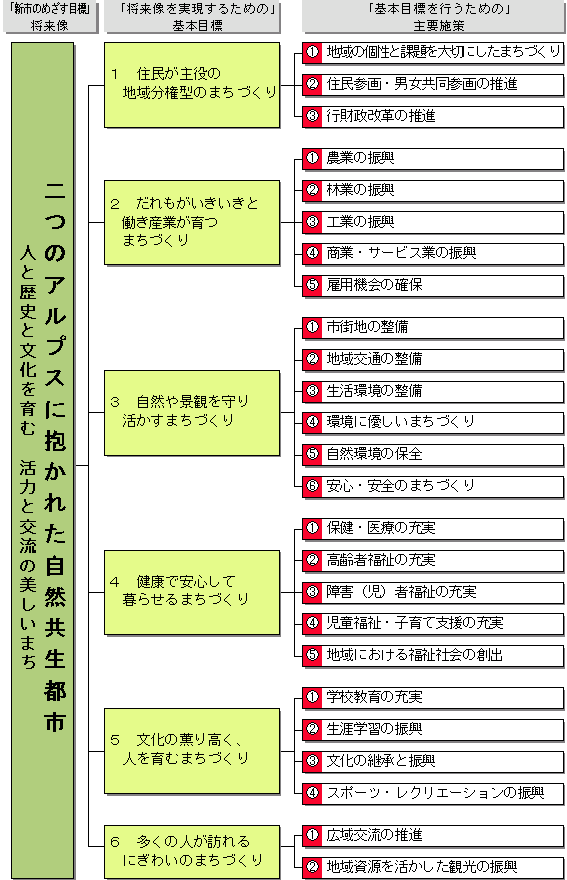
基本目標  |
住民が主役の地域分権型のまちづくり |
|---|
地方自治体は厳しい財政状況の一方、住民との協働の推進やきめ細かな課題への対応が求められており、自己決定・自己責任の原則に基づいた自立可能な分権型の自治をめざす必要があります。
このため、個々の地域の課題に対して、きめ細かく対処できるような地域内分権の仕組みづくりを進めます。
また、住民サービスや自治のあり方を見直し、住民と行政の役割分担による新たな協働の関係をつくります。
さらに、行財政改革を徹底し、自立可能な行財政基盤の確立と健全で持続可能な行財政システムを構築します。
 [1] 地域の個性と課題を大切にしたまちづくり
[1] 地域の個性と課題を大切にしたまちづくり
市町村合併により懸念される周辺地域の課題の解決を図るためには、地域内分権を進める必要があります。このため、旧町村役場を総合支所に位置づけて、現在の行政サービス水準の維持を図るとともに、地域自治区等の新たな制度を活用しながら、予算や事務事業の執行に一定の権限を持たせるよう配慮します。
一方、地域内分権のためには、地域組織を確立し、住民自治を強化することも重要であり、各地の地域活動をさまざまな方法で支援していきます。このため、活動の拠点となるコミュニティ施設の整備を進めます。また、住民意識の醸成を図るために、リーダーの育成や地域イベントの活性化を図ります。
 [2] 住民参画・男女共同参画の推進
[2] 住民参画・男女共同参画の推進
住民のまちづくりへの参加意識が高まり、住民・企業と行政との役割を分担しながら、互いに協力しあう協働のまちづくりを進めます。
このため、若者の流出や超高齢化によって集落の基本的な運営に支障をきたしているところについては、小集落の再編成や集落の運営支援など具体的対応策を図っていきます。
また、住民への情報公開を徹底し、ワークショップ ※22 やパブリックコメント ※23 の導入等、住民との対話を重ねながら計画や事業を推進していく仕組みづくりを進め、住民の行政への参画機会を拡大します。
一方、男女共同参画社会の実現に向け、意識啓発の推進、女性の参画機会の拡大や男女がともに活躍するための支援体制の強化を図ります。
 [3] 行財政改革の推進
[3] 行財政改革の推進 市町村合併を契機に、行政改革や財政効率化を積極的に進め、健全な財政基盤を確立することが求められています。このため、住民サービスの向上を図りつつ、民間委託の推進やPDCAサイクル ※24 等の民間企業の経営手法の導入、情報システムの活用による電子自治体の構築を進めながら、戦略的な行政運営をめざします。財政面では、厳しい財政状況に対応して、簡素で効率的な財政運営を行うと共に重点的な配分・投資を行っていきます。また、住民への情報公開を徹底し、行政評価等のシステムを構築していきます。さらに、地域住民に任せられることはできるだけ任せるために、NPO、地域団体、民間団体との協働も進めます。
|
| 主 要 施 策 | 施 策 概 要 |
|---|---|
| 地域の個性と課題を大切にした まちづくり |
・地域活動がしやすい環境づくりへの支援 ・地域の個性を活かした地域内分権の推進と総合支所機能の充実 ・住民の交流や生涯学習拠点としてのコミュニティセンターの整備 ・過疎・辺地計画と山村振興等による周辺部対策の推進 ・新市の一体感の醸成や旧市町村単位の地域振興のための基金の積み立て ・水源地域活性化のための各種ビジョンや提言を活かした施策の推進 など |
| 住民参画・男女共同参画の推進 |
・住民と行政による協働のまちづくりの推進 ・会議などの情報公開制度の充実と透明性の確保 ・すみよい地域づくり計画の推進・拡充 ・男女共同参画社会の実現 など |
| 行財政改革の推進 |
・効率的な行財政運営と抜本的な行財政改革 ・住民ニーズに迅速に対応したサービスの充実 ・職員の資質の向上と定員管理の適正化 ・ボランティアグループやNPOなど住民活動への支援 ・行政情報を迅速かつ正確に伝達するための電子自治体の推進 ・総合計画や個別計画などの計画行政の推進 ・収納率の向上による自主財源の確保や国県制度の有効活用 ・受益者負担の原則に立った使用料・手数料等の適正化と公平化 ・予算の適正配分や経費の節減による健全財政の堅持 ・行財政評価システムの導入による事業評価制度の構築 など |
基本目標  |
だれもがいきいきと働き産業が育つまちづくり |
|---|
地域の経営については、国からの支援が期待できなくなるなどの変革期を迎えており、地域間競争を生き抜くためには、産業振興などを進めて地域全体の自立性を高める必要性があります。
農業では、低農薬、無農薬の取り組みや、有機農業等による品質の向上を図り、収益性向上をめざすとともに、現在ある特産品の知名度アップや地場産品の売り込み、特産品の開発や加工品の多様化、体験・観光農業の振興等を図ります。また、林業では、森林の保健休養等の公益的機能も重視しながら、関連する地場産業の振興を図ります。
工業は、既存の精密機械、電気機械等のハイテク産業の振興を進めるとともに、新産業の創出や新事業の展開、研究開発型企業の誘致を図ります。商業・サービス業では、幹線道路沿いに立地する沿道型商業施設と既存の小売店舗の連携を強め、歩行空間の整備等により、回遊性のある商店街の形成に努め、活気ある商業のまちづくりを推進します。
さらに、環境や情報、福祉等をテーマとする新たな企業の誘致・育成を図り、若年層の就業機会の確保と多様な就業構造を有する産業のまちづくりを推進していきます。
 [1] 農業の振興
[1] 農業の振興
新市には、基盤整備の進んだ広大な農地がありますが、近年の農業を取り巻く環境はますます厳しくなっており、農業従事者の減少が続いています。そこで、今後も引き続き、土地改良事業(用排水路・農道整備等)、その他の農業生産基盤整備により、優良な農地の保全を図ります。また、市街化の進展に対し、農地以外の土地利用との調整を図り、農地としての機能の低下を防ぎます。
また、高齢化等が進み担い手不足等による耕作放棄地などの遊休農地や荒廃農地をなくすため、営農支援センターなどを核に農業法人や協業組合に対する支援、集落営農等に向けた取り組みを行っていきます。
さらに、グリーンツーリズムやりんごオーナー制度などの観光農業の推進、新たな農産物流通の仕組みづくり等により、農業経営の近代化、高付加価値型農業への転換、農家所得の向上等をめざし、ブランド米の売り出しや、花卉栽培の取り組みも積極的に進めます。また、地産地消の積極的な取り組みを行っていきます。
このようにして、農業経営の向上、農業の魅力向上等を図りながら、後継者の育成や新規営農者の支援を進めるとともに、有害鳥獣対策を進めることにより生産意欲の低下を防いでいきます。
一方、中山間地では、農業においても条件が不利であることから、支援策を充実し、農業の維持・振興を図ります。
 [2] 林業の振興
[2] 林業の振興
林業については、わが国全体の社会経済の変化により産業としての状況は一層厳しい環境にありますが、林業基盤整備の推進を図るとともに、保育、間伐等の維持管理を支援する中で、持続的な森林資源の維持・造成に努めます。
特に、森林のもつ多面機能の重要性をよく認識し、手入れがされずに放置されている山林などの減少を図るため、保安林の指定及び改良、保育事業の導入にあわせ、森林アドバイザーの活用や森林組合等との連携を強化していきます。
一方、森林保全や国土保全の面からも過疎対策の充実を図り、山村の振興を進めます。
 [3] 工業の振興
[3] 工業の振興
本地域の工業は、電機・機械・精密等のハイテク産業を中心に発展してきましたが、近年の景気の低迷から脱しておらず、順調に推移してきた工業製品出荷額等は停滞状態にあります。
新市は東京圏・名古屋圏に比較的近いというメリットを活かし、新しい産業立地の受け皿となることが期待されるため、地元の大学や高校などの研究機関と連携しつつ先端産業や研究開発型企業の誘致、ベンチャー企業等の育成を図ることが必要です。一方、既存企業については、研修機会づくりの支援や中小企業融資の拡充等により、経営の安定化等の支援を行っていきます。
また、新分野へ進出する企業に対しての支援を積極的に行っていきます。
 [4] 商業・サービス業の振興
[4] 商業・サービス業の振興
新市には、伊那市の中心部に中核となる商業集積がありますが、近年では幹線道路沿いに大型の量販店等の進出が顕著になっています。また、伊那市の商業施設には、周辺市町村からの買い物客も集まってきていますが、買い物客の満足度を満たすことができないものについては、諏訪・松本方面等まで買い物に出かけている状況があります。
このため、既存の商業施設の積極的な取り組みを支援することで、より魅力ある商業集積地とする施策を推進する必要があります。そのため駐車場や歩道等の環境整備、空き店舗対策やイベントの開催等への取り組みに対する支援を推進します。また、金融機関やサービス業等のオフィスの立地も促進します。
一方、高遠地区では城下町としてのまちなみを、長谷地区では南アルプス観光の入口という特性をそれぞれ活かし、観光客が楽しめる商店街づくりを進めます。
 [5] 雇用機会の確保
[5] 雇用機会の確保 地域の過疎化や高齢化の原因となっている若年層の流出を抑制し、さらにUターン・Iターン・Jターンによる定住を進めるためには、魅力ある教育機会、就業機会、定住環境を提供する必要があります。このため有効求人倍率の比較的良いとされる地域にあっても、既存の企業等の雇用拡大を図るとともに、新たに誘致することでより多くの就業の機会の確保を図ることが求められます。また、環境、情報、福祉等の新しい分野の起業化や、若者への起業支援も進めます。
|
| 主 要 施 策 | 施 策 概 要 |
|---|---|
| 農業の振興 |
・優良農地の保全や畑作営農の振興などによる農業生産の振興 ・農業近代化施設の整備や土地基盤整備の推進 ・担い手の育成や集落営農に向けた農事活動法人組織の設立支援 ・地域資源を活かしたブランド戦略の推進と農地の集積 ・グリーンツーリズムの推進などによる農村の活性化 ・有害鳥獣対策の推進 ・遊休農地や荒廃農地の防止及び利活用 など |
| 林業の振興 |
・森林の保護と意識の高揚 ・造林の推進や間伐材の利用促進などによる林業の振興 ・水源かん養林や保安林の整備や平地林等の整備による総合利用の推進 ・森林の公益機能の推進 ・不在者山林などの未整備山林の整備促進 ・有害鳥獣対策の推進 など |
| 工業の振興 |
・企業の育成や、産官学連携による新事業展開による工業の振興 ・中小企業融資の拡充 ・住環境の整備や融資制度の充実による人材の育成支援 ・新産業の創出や創造的企業の創出支援 ・地域の活性化や就労の場を確保するための企業誘致の促進と支援 ・経営・技術指導の充実による経営基盤の強化 ・Uターン・Iターン・Jターンの促進 など |
| 商業・サービス業の振興 |
・商業・サービス業の振興のための積極的な取組みへの支援 ・魅力ある商業基盤の整備と周辺環境の整備・活用 ・空き店舗対策や魅力ある活性化イベントの推進 ・人材の育成や経営指導の充実等による経営の安定化 ・地域の特性を活かした観光客が滞在できる商店街づくり など |
| 雇用機会の確保 |
・魅力ある教育機会・就業機会・定住環境の提供 ・就業能力の開発促進と新卒・女性・高齢者雇用の促進 ・企業の雇用拡大など官民一体となった施策の展開 ・シルバービジネス ※25 などの新分野の起業化や若者の起業支援 ・未組織労働者の福祉の増進 など |
基本目標  |
自然や景観を守り活かすまちづくり |
|---|
新市は、二つのアルプスの山なみや三峰川・天竜川等の良好な自然環境に恵まれており、ハッチョウトンボやホタル、イワナ等の希少な野生の動植物も生息しているため、これらの豊かな自然環境を住民と行政等が協働して守っていきます。
また、ごみや処理が不適切な排水による汚染を防ぎ、太陽光やバイオマス ※26 等の自然エネルギーを活用することで、環境に優しいまちづくりを進めます。
さらに、道路、下水道、ごみ処理等の生活基盤の整備・充実を図り、自然環境を保持しながら快適な暮らしの実現を図ります。
一方、住民生活の安全を図るため、消防・防災体制の強化、豊かな自然との共生を図りながらの治山・治水事業等を進めます。
 [1] 市街地の整備
[1] 市街地の整備
近年は、無秩序な都市開発は減少していますが、今後も引き続き乱開発を抑制し、バランスのとれた市街地の形成をめざすことが必要です。このため、都市計画の策定等を通じて、計画的な市街地の整備と土地利用の誘導を図る必要があります。
また、都市計画事業については、今後も円滑な事業推進を図ります。
 [2] 地域交通の整備
[2] 地域交通の整備
新市では、中央道、国道153号、152号、361号のほか、主要地方道、一般県道、広域農道等が整備されています。さらに、権兵衛峠道路が開通し、153号伊那バイパスや152号バイパス等が整備されると、木曽方面との交流が活発化するとともに、東京圏・名古屋圏を結ぶ新たな交通・物流ルートが形成されることも期待されています。
そこで、こうした広域幹線道路の整備を受け、新市の都市計画道路及び幹線道路の計画的かつ体系的な整備を進めます。また、市街地や観光地における駐車場等の整備を進めます。生活道路については、通過交通と生活交通の分離を図るようにして整備を進めます。さらに、自転車道や歩道の整備を進めるとともに、まちなかのバリアフリー化 ※27 を進めます。
また、地域路線バスの利便性の向上や、市内の主要拠点を結ぶ循環バスの導入を図り、住民の利便性の向上を図ります。
 [3] 生活環境の整備
[3] 生活環境の整備
新市は、広大な土地と水、四季折々に変わる自然が豊かで、また農作物等の自然の恵みも豊富な地域であり、快適な暮らしの基礎的条件が整っている地域です。公園、住宅、下水道、ごみ処理等の整備を行うことで、より美しく快適な生活環境の創出をめざします。
公営住宅については、人口減少地域における定住対策の一環として、一定の整備を進めるほか、老朽化が進んでいるものについては、計画的な改修等を図ります。
ごみ処理については、住民意識の高揚を図りながら、ごみの発生抑制・減量化・分別収集を進めます。また、リサイクル運動の拠点となる施設や収集体制を整備し、住民が積極的に再資源化に取り組めるようにしていきます。
下水処理については、公共下水道や、農業集落排水、合併処理浄化槽等の方式がありますが、各地区の事情に適した下水処理計画に沿って整備を進めます。また、既に整備されている施設等についても適正な汚泥処理を含めた維持修繕を進めます。
交通安全については、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の整備を進めるとともに、市街地では歩道の整備などを進めます。また、住民の交通安全意識の高揚を図るため、自動車の運転者だけでなく、自転車利用者や歩行者等交通弱者に対する交通安全教育を進めます。
上水道については、水道事業の経営効率に配慮しながら、水質の維持に努め、あわせて水の安定供給を図ります。また、老朽化が進みつつある既存の配水管等の施設の更新や耐震補強等の整備を進めます。
公園については、住民の意向を踏まえながら整備を進め、良好な維持・管理に努めながら、高齢者でも散策しやすく子どもを安心して遊ばせることのできるようにしていきます。
これらの施策展開を通じて、豊かな生活環境を実現し、さまざまな世代の人々の定住を図っていきます。
 [4] 環境に優しいまちづくり
[4] 環境に優しいまちづくり
これからのまちづくりにおいては、地域の中に限らず、広く地球環境の視点に立って環境に優しいまちづくりを進める必要があります。
このため、地球環境問題への理解を深め、住民、企業、行政が連携を図りながら、CO2排出削減等の取り組みを進めます。また、リサイクル運動の拠点となる施設や収集体制を整備し、住民が積極的に再資源化に取り組めるようにしていきます。さらに、省エネルギー化を推進するとともに、風力や太陽光、バイオマス等の地域新エネルギーの利用を検討・推進します。
一方、こうした環境に優しい行動を着実に推進していくために、行政や企業のISO14001 ※28 の取得等を促進します。
 [5] 自然環境の保全
[5] 自然環境の保全
自然との共生を図る地域の実現に向けては、森林等を住民全員で守っていくことが重要です。また、三峰川をはじめ地域内の河川の清流を守るためには、住民自らこれらの河川について理解を深めるとともに、ふれあえる場の確保が重要となります。さらに、広域的な連携のもとで、流域が一体となった水質保全活動等を行っていきます。
一方、新市のように自然豊かな地域においては、自然に学び、自然と共生する中で、災害に強いまちづくりを進める必要があり、河川や森林の整備や治山治水対策の推進を図る必要があります。
 [6] 安心・安全のまちづくり
[6] 安心・安全のまちづくり 新市の防災対策としては、新潟中越地震等の教訓も活かしながら、地震や風水害等の災害が発生した場合でもいち早くライフラインや情報通信手段が確保できる体制をとり、住民の安全を守ります。また、自主防災組織の育成や、防災訓練の充実を図り、住民自ら守るという防災意識の高揚を図ります。さらに、近隣市町村等との連携を進め、災害時に相互に応援する広域防災体制の確立を図ります。
消防については、消防機動力の増強を図るため、消防施設の適切な配置と整備を図るほか、資機材や装備を最新のものに更新していきます。また、地域住民と一体となった消防団活動の充実を図ります。
救急医療については、総合医療体制の拡充・強化を図るとともに、市内のどこに住んでいても安心できる救急医療体制の充実をめざします。
|
| 主 要 施 策 | 施 策 概 要 |
|---|---|
| 市街地の整備 |
・計画的な市街地整備と土地利用の適正化 ・計画的な都市計画事業の推進 ・地域活力を活かした市街地再開発の促進 ・区画整理による市街地の整備 ・景観に配慮した町並みの整備促進 など |
| 地域交通の整備 |
・国道・主要地方道・県道などの広域幹線道路網の整備促進 ・地域幹線道路ネットワークの構築と計画的・体系的な道路網の整備 ・循環バスや主要拠点等を有機的に結ぶ公共交通機関の確保と利便性の向上 ・老朽化による橋りょう等の整備推進 など |
| 生活環境の整備 |
・公営住宅の整備と民間活力の導入による宅地開発の推進 ・ごみ処理の広域化の推進と減量化の推進 ・衛生的で文化的な下水道等の整備・普及と施設の適切な維持管理 ・ガードレールや歩道、道路照明など交通安全施設等の整備 ・安全でおいしい水道水の安定供給と施設の適切な維持管理 ・自然景観に配慮した景観の保全と住民協定の推進 ・し尿処理施設や公衆トイレ、火葬場などの生活衛生施設の整備 ・住民の憩いの場としての公園・緑地の整備 ・公害防止施策の継続 など |
| 環境に優しいまちづくり |
・リサイクルの推進 ・風力・太陽光・水力・バイオマスなどの新エネルギーの利活用 ・環境基本計画の推進 ・地球環境の保全と、循環型社会の構築 ・国際環境規格ISO14001の適正な運用 など |
| 自然環境の保全 |
・自然環境の保全と森林の持つ公益的機能の保持 ・自然に親しむためのイベントの実施 ・希少動植物の保護 ・河川・水路などの災害危険区域の改修促進 ・治山・治水対策事業の促進 ・三峰川総合開発事業の促進 など |
| 安心・安全のまちづくり |
・地域防災計画の策定 ・消防団員確保による活性化と消防機動力の増強 ・自主防災組織の充実 ・広域消防体制強化に向けた消防・防災体制の充実と施設の整備 ・防災・同報無線の整備による防災情報の収集と伝達体制の強化 ・高度救命資機材の整備による救急・医療体制の充実 ・救助用資機材の充実による救助体制の整備 など |
基本目標  |
健康で安心して暮らせるまちづくり |
|---|
保健・医療面では、地域の衛生環境の向上を図るとともに、効率的な地域医療体制の確立や特徴ある地域医療の充実をめざします。また、住民の健康維持・増進を図るため、身近な健康づくりやスポーツ等の参加機会を増やします。
福祉については、少子・高齢化社会の到来を受け、高齢者福祉の推進を図るとともに、子育て支援も強化し、乳幼児から高齢者まで誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。こうした福祉政策の推進においては、在宅での対応、近隣地域内での対応、公的施設での対応という優先順位のもとで、効率的に実施されるよう支援していきます。
 [1] 保健・医療の充実
[1] 保健・医療の充実
病気やけがをしても安心して治療できるようにするために、医療施設の整備充実を図ります。新市の医療全体の効率化を図るために、身近な地域医療を担う診療所から高度な治療が受けられる伊那中央病院等の総合病院までを体系的に連携させ、住民のニーズや容態に応じて適切な医療を受けられる環境をつくります。
また、長谷の「気の里」・「癒しの里」の構想としての取り組みを促進し、心身ともに健康な住民を増やすとともに、他地域の住民がリフレッシュに訪れるような地域づくりをめざします。
 [2] 高齢者福祉の充実
[2] 高齢者福祉の充実
急速に高齢化が進む社会において、高齢者が健康で安心して暮らせるような福祉サービスを安定的に実施するためには、介護保険制度を踏まえながら福祉施策の充実と効率化を両立する必要があります。このため、在宅福祉サービスの充実を図り、その上で各地域のニーズを把握しながら、計画に沿った高齢者福祉施設の整備拡充を図ります。
また、新市において高齢者の中には、元気があり生きがいを持って働く方も多くいます。そこで、高齢者の起業化や就業を支える、シルバービジネスの振興やシルバー人材センター ※29 の充実を図ります。さらに、高齢者の豊富な知識や経験を活かした観光ガイドや、生涯学習講師等のボランティア活動を推進します。
 [3] 障害(児)者福祉の充実
[3] 障害(児)者福祉の充実
障害(児)者福祉については、障害(児)者が地域社会の中で自立し、安心して生活することができるように、共同作業所の充実など障害(児)者を支援する体制の整備やサービスの充実を図るとともに、社会参加のための支援を行います。
さらに、高齢者や障害(児)者の社会参画を推進するための基盤として、循環バス等の公共交通の充実やバリアフリー住宅 ※30 の普及促進を図ります。
 [4] 児童福祉・子育て支援の充実
[4] 児童福祉・子育て支援の充実
従来の保育サービスに加え、延長保育、一時保育等、利用者の保育ニーズにあったきめ細かなサービスを提供します。また、育児に関する悩みを気軽に相談できるような相談窓口を整備します。
さらに、幼児や児童と高齢者が交流をしやすい環境の整備を図ります。
子育て支援の分野においては、元気な高齢者や父親・母親等の積極的な参加を支援しながら福祉行政の効率化を図ります。また、地域における子育て支援の拠点として、子育て支援センターの整備を進めます。
 [5] 地域における福祉社会の創出
[5] 地域における福祉社会の創出
住民の地域福祉に対する意識の高揚を図るとともに、社会福祉協議会等との連携を図りながら、地域ぐるみできめ細かな福祉活動を進めます。また、広がりつつある福祉ボランティア活動の一層の支援を図ります。
また、さまざまな理由で社会的援助を必要とする住民に対しては、生活保護等の支援とともに、相談機能の充実を図り、生活の安定を支援していきます。
こうした地域福祉活動を支援するために、拠点となる施設の整備・充実を図ります。
|
| 主 要 施 策 | 施 策 概 要 |
|---|---|
| 保健・医療の充実 |
・自主的・継続的な健康づくり運動の推進 ・生活習慣病予防などの健康づくり事業の推進 ・診療所等における診療機能の拡充など地域医療サービス体制の充実 ・旧伊那中央病院跡地利用による保健・福祉の拠点整備 ・伊那中央病院の増床計画や24時間緊急医療体制など高度医療体制の強化 ・国民健康保険事業の推進 など |
| 高齢者福祉の充実 |
・一人暮らしや高齢者世帯の生活サポートの充実 ・元気なお年寄りの生きがいのある生活に向けた支援と介護予防の充実 ・介護保険事業の推進 ・高齢者の日常の交通手段の確保や安全対策などの環境整備 ・高齢者の支援施設・支援センター等の整備 など |
| 障害(児)者福祉の充実 |
・障害(児)者の居宅生活の支援と居宅介護サービスの推進 ・共同作業所の整備などの障害(児)者の自立支援 ・低所得者への支援の充実 ・バリアフリーなどの住環境整備への支援 ・障害(児)者の日常の交通手段の確保や安全対策などの環境整備 ・障害(児)者の支援施設・支援センター等の整備 など |
| 児童福祉・子育て支援の充実 |
・保育所の適正配置や保育内容の充実による保育所の適正運営 ・学童保育や一時保育などの保育サービスの充実 ・安心して子供を生み育てることができるような支援の充実 ・子育て支援センターの整備と支援体制の充実 ・母子・父子福祉に向けた相談・支援体制の推進 ・生活援護制度の運用と自立の支援と相談指導の充実 など |
| 地域における福祉社会の創出 |
・地区社会福祉協議会の充実 ・ボランティアや住民主体の地域福祉活動の支援 ・地域福祉計画の策定と地域福祉活動の推進 など |
基本目標  |
文化の薫り高く、人を育むまちづくり |
|---|
未来を担う子どもたちの教育については、学校と家庭及び地域が一体となって取り組む必要があります。地域の自然・歴史・文化について学ぶとともに、国際感覚豊かな、時代の先端にふさわしい人づくり、互いに助け合い協力し合う人間性豊かな人づくり等を進めます。また、年齢や職業を超えたあらゆる人々が地域の伝統、文化等を学べるよう生涯学習の充実を図ります。
長い歴史に育まれた伝統・文化は、住民の誇りとして、継承者への支援を図っていきます。また、住民の文化活動の振興を図るとともに、新しい文化の誘致・育成も図ります。
さらに、住民の日常的な健康づくりを促進するために、スポーツやレクリエーション活動の振興を図ります。
 [1] 学校教育の充実
[1] 学校教育の充実
新市においては、国の教育改革も踏まえつつ、子どもたちは新市の将来を担う貴重な共有財産であるという認識のもと、地域に即した教育振興を図っていきます。
確かな学力を身につけるため、全市の小中学校の教育目標の中心に「基礎基本の定着と伸びる力を伸ばす」ことを据え、少人数指導等を充実させ、「わかる授業」の実現に努めます。
また、総合的な「生きる力」という観点から、地域の自然の恵みや歴史・文化の豊かさを理解し感謝し、これを尊重し継承する精神を育みます。さらに、国際化時代に生きる広い視野を具備するとともに、社会的弱者へのいたわり・思いやりの心を持つような人間性にあふれた未来の社会人を育てるため、さまざまな体験学習を展開し、大都市圏の子どもたち・外国籍の人々・お年寄りなどとの交流も積極的に推進します。
これらの学習は、学校教育だけでなく、地域の多様な体験や知識を有する人材を活かしながら、「地域の子どもは地域で育てる」体制づくりとともに進めます。
一方、保育所・幼稚園と小学校の連続性、小学校と中学校の連続性を確保するための組織的検討、通学区の弾力化、地域の高校存続と改革の促進などの課題にも積極的に取り組みます。さらに、耐震改修など教育施設の整備を図り、教育環境の充実に努めます。
 [2] 生涯学習の振興
[2] 生涯学習の振興
新市の自然や文化や産業等の地域の特徴を活かしながら、生涯学習を進め、若者からお年寄りまで、誰もが興味を持って学ぶことのできる環境づくりを進めます。特に、新市の重点課題である「自然との共生」や「産業活力の創造」に向け重点的に人材育成に努めます。
このため、生涯学習活動の拠点となる公民館・生涯学習センターや図書館等の整備・充実を進めるとともに、グループ・サークル活動の支援や、意欲ある指導者の育成を図ります。また、生涯学習に関する情報提供や相談体制の充実を図ります。
さらに、信州高遠少年自然の家との連携を一層深め、地域と一体となった施設活用による生涯学習の振興に努めていきます。
また、青少年の健全育成に向けて、地域で青少年を育てる環境づくりを進めるなど、指導体制の充実等を図ります。
 [3] 文化の継承と振興
[3] 文化の継承と振興
城下町であった高遠の歴史や文化を始め、各地の伝統芸能等の文化を継承していくことが求められており、文化財の保存も進めていきます。
また、本地域から輩出された芸術家たちの偉業をたたえ、美術や音楽等の芸術文化を発展させていくとともに、住民の文化活動の支援や文化グループ同士の連携を促進します。
 [4] スポーツ・レクリエーションの振興
[4] スポーツ・レクリエーションの振興
自由時間の増加や健康意識の高まり等により、住民のスポーツやレクリエーションに対する要望は増大し、多様化しています。新市では、各地でスポーツ施設の整備が進みつつあり、これらの充実を図るとともに、利活用を進めます。
また、競技スポーツの水準の向上や市民スポーツの普及を進めるために、体育指導委員やその他のスポーツ指導者の育成を図ります。さらに、誰でも気軽に参加できるようなスポーツイベント等を開催します。
さらに、住民のスポーツへの関心を一層高めるとともに、新市のイメージアップのため、既存の大会を全国規模に育てたり、全国的な大会の誘致に取り組みます。
| 主 要 施 策 | 施 策 概 要 |
|---|---|
| 学校教育の充実 |
・特色ある教育の推進 ・人権・環境・心の教育などの教育の内容の充実 ・老朽校舎の増改築や耐震化、安全性を重視した施設の整備 ・少人数学級や地域との連携を密にした教育環境の充実 ・保育園や小学校相互の連携強化 など |
| 生涯学習の振興 |
・生涯学習センター等を核とした推進体制の充実 ・公民館や図書館などの生涯学習関連施設の整備充実 ・クラブ・サークル活動への支援や指導者の発掘などへの活動援助 ・公民館の学級・講座や分館活動の充実による学習機会の充実 ・青少年の健全育成を図るための地域ぐるみの環境づくり ・人権教育の充実 など |
| 文化の継承と振興 |
・芸術・文化の鑑賞機会の充実や文化意識の高揚 ・文化・サークル活動の育成と市民文化活動の推進 ・芸術・文化施設の整備・充実 ・歴史・文化財等の適切な保存と整備・充実 ・伝統文化・歴史・民俗芸能の継承と復活 など |
| スポーツ・レクリエーションの振興 |
・生涯スポーツの普及 ・スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 ・スポーツ・レクリエーションイベントの開催 ・競技力の向上 など |
基本目標  |
多くの人が訪れるにぎわいのまちづくり |
|---|
新市の山岳、高原、農地、平地林(里山林)等の美しい自然と歴史・文化を活かし、地域間での連携を図りながら、多くの人が訪れたくなるような交流・観光のまちづくりを進めます。交流や観光の振興にあたっては、グリーンツーリズム等で地域の資源を活かすとともに、情報や交通基盤の整備、住民のホスピタリティ ※31 の醸成等を図っていきます。
 [1] 広域交流の推進
[1] 広域交流の推進
地域内の交通網の整備により、新市の一体化を進めるとともに、地域外の各地と結ぶ広域交通網の整備やリニア中央エクスプレス誘致促進のほか、光ファイバー等の情報通信基盤の整備を関係機関へ働きかけ、地域間交流の活発化を図ります。また、こうした広域交流を活かしながら、にぎわいのあるまちづくりをめざします。
市内中心部においては、こうして訪れた人々が楽しく滞在できるよう、魅力ある中心市街地の整備を進めます。また、その他の地域においても、道の駅等の交流施設や観光施設を活かしながら、広域交流の拠点づくりを進めます。
地域情報化については、情報通信基盤の整備を進めるとともに、地域内のさまざまな施設を結ぶ情報ネットワークの構築を図ります。また、情報関連産業の育成を図り、経済の活性化や若年層の定住促進等にも寄与しています。
一方、住民の国際理解を深め、国際的な人材の育成を図るために、姉妹都市交流をはじめとする国際交流事業を推進するとともに、民間で実施している国際交流を支援します。
 [2] 地域資源を活かした観光の振興
[2] 地域資源を活かした観光の振興
新市の恵まれた自然、歴史、文化を活用しながら、多くの人が年間を通じて訪れてみたくなるような観光のまちづくりを進めます。このため、伊那市のみはらしファーム、高遠町の高遠城址公園、長谷村の南アルプスや三峰川源流域の豊かな自然といった各地の優れた観光資源を核に、広大な美しい平地林の活用、新しい観光資源の掘り起こし、桜を核にした花からのまちづくりを進める住民組織等への支援、市内観光地相互の連携、木曽地域や諏訪地域、伊南地域との間で広域的な観光面の連携等を進めていきます。
また、農業体験を含めたグリーンツーリズム、地域の工場等を見学する産業観光等の振興を図り、地域の各種産業と観光との連携を進めます。
さらに、こうした観光資源を広く内外にPRするとともに、外国語による情報システムの導入、観光施設のユニバーサルデザイン化* 等を進め、外国人や障害(児)者・高齢者等のあらゆる人が訪れたくなるようなまちづくりを進めます。
こうした観光客に対しては、新市の住民全員が案内人となり、もてなしができるようにし、ホスピタリティの面でも優れた観光地をめざします。
|
| 主 要 施 策 | 施 策 概 要 |
|---|---|
| 広域交流の推進 |
・友好都市との交流の促進 ・他地域との広域交流の促進 ・広域交流の拠点づくりの推進 ・国際化への対応 など |
| 地域資源を活かした観光の振興 |
・通年観光に向けた観光戦略の展開 ・権兵衛峠道路開通に向けた広域観光の推進 ・観光資源の再発見と整備・充実 ・魅力ある特産品の開発や情報発信・イベントなどの充実 ・他産業との連携強化 ・広域連携による観光振興 など |
新市のまちづくりに際して、特に重点を置いて実施すべきプロジェクトをリーディングプロジェクトと位置づけます。
リーディングプロジェクトの実施にあたっては、財政への影響や地域にもたらす効果等を考慮するとともに、住民参加の意向の把握、関係者の意見の反映に努め、住民自らが考えて行動していくことが必要となります。
合併を契機に市町村の一体化を進めることが重要であり、そのために、各地区を結ぶ道路の整備や循環バス等の公共交通の整備を推進します。また、権兵衛峠道路の開通等により、新市を巡る広域的な交通にも変化がもたらされることが予想されます。このため、通過交通の円滑化を図る一方、生活道路の整備や歩道などの交通安全施設の整備を進め、住民生活における安全の確保を図ります。さらには、上伊那の交通の要衝としての利点を活かし、上伊那の中核都市をめざします。
- 【 関連事業 】・ 国道153号伊那バイパスや152号バイパス等の整備促進
・ 東西交通確保のための環状道路や幹線道路の整備
・ 権兵衛峠道路開通後の交通安全施設等の整備
・ 地域を結ぶ循環バスの整備や日常の交通手段の確保
・ 特急列車の飯田線乗り入れの促進
・ 権兵衛峠道路を利用しての名古屋圏への利便性の向上施策 等
権兵衛峠道路の開通等により、新市と木曽方面や諏訪方面、飯田下伊那などとの交流や連携が活発化することが予想され、特に広域観光ルートの形成が急務とされています。
また、中央アルプスと南アルプスの山岳観光の連携促進のため、長谷村と駒ヶ根市を結ぶ道路整備の期待も高まっています。このため、既存の観光資源、観光施設のリニューアルを図るとともに、新たな観光資源の掘りおこしを進め、新市全体の観光振興を進めます。
- 【 関連事業 】・ 権兵衛峠道路の開通を見据えた広域観光戦略の展開と施設整備
・ 高遠城址公園やみはらしファーム、南ア林道バス等を核としての観光客の誘致
・ 新市のブランド化に向けたPR戦略の強化
・ 高遠少年自然の家やキャンプ場などを活用した体験型観光の推進
・ 桜やアルストロメリアといった「花」をテーマにしたまちづくりの推進
・ 温泉入浴施設等を活用した通年観光の振興
・ 二つのアルプスにまたがる広域観光ツアー等の企画と観光連携
・ 史跡・歴史・文化を活かした観光客の誘致 等
新市には、さまざまな優れた技術を持った企業が集積しています。また、新市及び周辺の学術・研究機能を活かしながら、新事業の創出等をめざすことが期待されています。
そこで、このような優れた技術を交流・融合させることによって、さらに高度な技術を生み出し、産業化していくことが重要であり、技術交流を活発化する仕組みづくりを進めます。
また、農林業については、品質のよい農林産物の生産に力を入れ、都市住民との交流等を活かしながら産業全体の振興を図ります。
さらに、商業・サービス業については、にぎわいのある商店街の創出や新しいサービス業の振興等に力点をおいて振興を図ります。
- 【 関連事業 】・ 産官学連携や異業種交流等の推進
・ 起業家や新事業開発支援の推進
・ 技術力の高い企業誘致の推進
・ 新分野進出企業への支援
・ 地域資源を活かしたブランド戦略の推進
・ 集落営農の推進による農業の堅持と農地の保全
・ 魅力ある商業基盤整備と周辺環境の整備・活用 等
新市の中には、過疎化が進むと懸念される地域があります。しかし、過疎であることを逆手にとることにより、むしろ、アウトドア志向・田舎住まい志向の大都市圏の人々にはより魅力的な地域となると考えられます。
そこで、風土(過疎地域の資源や歴史的資源等)を最大限に活かすようなまちづくりを積極的に進め、交流の拡大から定住を促進します。
- 【 関連事業 】・ 公営住宅の整備や宅地開発等の推進
・ 地域の特色を活かした個性ある学校教育の充実
・ 学トピア構想、気の里構想の推進
・ 若者が魅力を感じる都市基盤整備等の推進
・ 空き家アドバイザー等による空き家の活用
・ 少子高齢化地域の集落運営支援
・ その他各種定住支援策の促進 等
新市では、住民が主体となって行財政改革を徹底する一方、地域内分権のまちづくりを進めます。そこで、行政の情報公開と住民の知恵の結集の上で、行財政改革の監視システムを構築したり、まちづくりに住民の優れたアイディアを活かしたり、住民のさまざまな実践活動を支援していきます。
- 【 関連事業 】・ 総合支所の整備と機能の充実
・ 地域自治区等の設置
・ すみよい地域づくり計画の推進
・ まちづくりの主役としての高齢者参画の充実
・ 住民と行政との協働のまちづくりの推進
・ 情報公開の充実 等
一人ひとりが自己実現できるまちづくりの理念に沿い、まちづくりは人づくりの考えをふまえ、人材育成に力を入れたまちづくりを進めます。
このため、地域活動やボランティア・NPO活動を支援するとともに、すみよい地域づくり計画の充実を図りながら、まちづくりに資する優れた人材育成を進めます。また、子どもたちは新市の共有財産であるという認識の下、学校教育や地域教育の充実を図ります。
- 【 関連事業 】・ ボランティアグループやNPOなど住民活動への支援
・ 住民の交流や生涯学習拠点としてのコミュニティセンターの整備
・ すみよい地域づくり計画の推進・拡充
・ 家庭・地域・学校の連携による教育の推進
・ 高遠の「進徳館」の伝統を活かした人づくりの推進
・ グローバルで多様化した社会に対応できる人材の育成 等
自然環境や景観等に優れた新市のめざす自然共生都市の実現に向けて、住民や企業とも協働しながら積極的な環境保全施策の展開を図ります。自然環境や景観の保全については、住民の意識啓発によって生活を変えていくとともに、条例や都市計画等による保全の仕組みづくり、自然環境に配慮した公園等の整備を進めながら、実現していきます。また、リサイクルや花植え活動等の自然保護活動の推進については、住民と行政の協働を推進しながら実現していきます。さらに、省エネルギーや自然エネルギーの導入については、地域の企業等に積極的に働きかけるとともに、関連する企業の誘致を図ります。
- 【 関連事業 】・ 計画的な市街地整備と土地利用の適正化
・ 住民の憩いの場としての公園・緑地の整備
・ 自然環境の保全と森林の持つ水源かん養等の機能の保持
・ リサイクルの推進
・ 風力・太陽光・水力・バイオマスなどの新エネルギーの利活用
・ 花を活かした美しい景観の整備
・ ハッチョウトンボやホタルなどの希少動植物の保護 等
新市は長野県の南東部に位置し、東に南アルプス、西に中央アルプスを望み、天竜川や三峰川によって形成された肥沃な平地や、美しい河岸段丘など雄大な自然環境に恵まれています。また、桜の名所で知られる高遠城址公園をはじめとする観光拠点や広大な農地を利用した体験型農業、先端技術を持った産業集積など多彩な産業がいきづく地域です。さらに、中央自動車道や主要幹線道路などの幹線動脈上にあり、南信地域の中核都市として今後の発展が期待されています。
また、今後の地方自治は、住民に最も身近な基礎自治体である市町村が中核的な役割を担い、自己決定・自己責任の原則のもと、より自律的な行政運営が求められています。
こうした中で、新市においては、合併を大きな契機として、地域資源や地理的条件等を有効に活用しながら特色あるまちづくりを進めるとともに、住民参画を一層促進し、住民自治の充実を図ることが期待されています。
長野県は、「コモンズ ※33 からはじまる、信州ルネッサンス革命」の理念に基づき、「ゆたかな社会」の実現に向けて新市と十分に連携しながら新市の取組みを積極的に支援します。
 [1] 福祉施策の充実
[1] 福祉施策の充実 福祉サービスは、愛情、信頼といった人間の絆にもとづいて行われることが大切であり、それぞれの身近な地域ごとに人間の絆により支えあうシステム、すなわち「コモンズ」の観点を重視し、地域ケアの拠点となる宅幼老所や、障害(児)者が地域で自律して生活するためのグループホームなど、高齢者や障害(児)者が地域で安心して生活できるための在宅福祉の充実に向け支援を行うとともに、少子化対策や子育て環境の整備に対しても必要な支援を行います。
 [2] 保健・医療施策の充実
[2] 保健・医療施策の充実 新市や関係団体が行う健康づくりなどの保健活動に対する技術的支援を通じて、地域住民の健康増進を図ります。
 [3] 地域交通基盤の整備
[3] 地域交通基盤の整備 新市の一体化及び均衡ある発展を支援し、地域内外の円滑な交流を促進する観点から、国道・県道の計画的な整備に取り組みます。
 [4] 防災対策の推進
[4] 防災対策の推進
水害・土砂災害などを未然に防止するため、河川改修による治水対策、砂防事業などの必要な防災対策に取り組みます。
また、危険箇所の周知及び土砂災害警戒情報の提供などにも取り組みます。
 [5] 景観の育成
[5] 景観の育成 地域の歴史や文化、自然環境といったそれぞれの地域が持つ個性豊かな景観の保全、修復、創造を進めていくため、地域の方々の主体的な取り組みについて支援していきます。
 [6] 環境保全の推進
[6] 環境保全の推進 新市が行う環境への負荷が少ない持続的発展が可能な社会を形成するための取り組みを支援するとともに、事業所指導や環境測定などを通じ、地域における良好な生活環境の保全を図ります。
 [7] 産業の振興
[7] 産業の振興
技術革新による地域産業の高度化と産業創出や、各地域の観光資源を活用した誘客の促進を支援し、地域産業の活性化及び雇用の創出を図ります。
新市が取り組む中小企業、NPO、創業者等が行う健康・福祉、環境及び教育分野や地域資源を活用した新事業で地域経済の活性化、雇用の創出が見込める事業に対し、必要な資金を助成します。
地域の基幹産業のひとつである農業の生産振興や経営の安定を図り、併せて国土保全など農業・農村の持つ多面的機能を維持していくため、必要な用排水路、農道などの農業生産基盤の整備に取り組みます。
森林は、木材をはじめとした林産物の供給、水源のかん養、国土や自然環境・生活環境の保全、二酸化炭素の吸収を通じた地球温暖化防止、保健・文化・教育の場としての利用など多面的な機能を持っており、これらの機能が持続的に発揮されるよう森林を健全な状態で維持していくため、県民の理解と主体的な参加のもとで、適切な森林の整備に取り組みます。
|

