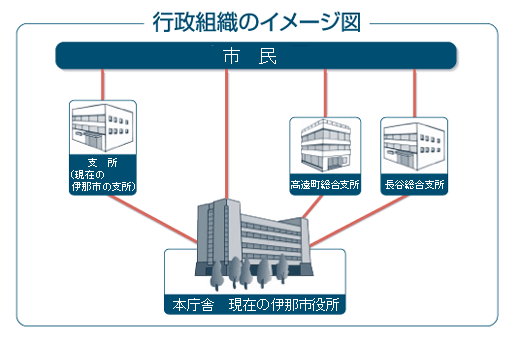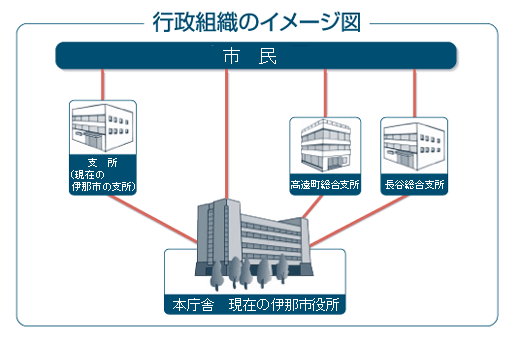窓口業務 窓口業務
- 本庁舎(現在の伊那市役所)、総合支所(現在の高遠町役場、現在の長谷村役場)、市民サービスコーナー、現在の伊那市にある支所で、各種証明書の発行及び生活に密着したサービスを行います。
- 時間外窓口発行サービスについては、自動交付機によるものに順次切り替えます。
- 各種証明書手数料は、合併時に統一します。
-
 水道料金 水道料金
- 水道料金は、現行のとおりとしますが、合併後6年目から統一料金とします。急激な変化を避けるために、旧市町村を単位として、最長5年間で段階的に調整を行います。
-
- ◎現行料金 (口径13mm)
-
| 区 分 | 伊那市 | 高遠町 |
長谷村 |
|---|
| 使用水量21m3/月の場合 | 3,626円 |
3,463円 | 2,920円 |
- ※標準的な家庭の場合
-
 下水道使用料 下水道使用料
- 下水道料金は、現行のとおりとしますが、合併後6年目から統一使用料とします。急激な変化を避けるために、旧市町村を単位として、最長5年間で段階的に調整を行います。
-
- ◎現行使用料
-
| 区 分 | 伊那市 | 高遠町 |
長谷村 |
|---|
| 使用水量21m3/月の場合 | 3,428円 |
3,559円 | 3,600円 |
- ※標準的な家庭の場合
-
 合併処理浄化槽設置補助金 合併処理浄化槽設置補助金
- 補助金は現行のとおりとしますが、合併後速やかに調整を図ります。
-
 ゴミの収集方法と手数料 ゴミの収集方法と手数料
- 可燃・不燃ゴミの収集方法・処理手数料は、広域事業で統一されているので現行のとおり実施します。
- 粗大ごみの収集回数は、伊那市については現行のとおり直接搬入のみとし、回収は行いません。高遠町・長谷村については、収集回数は年4回とします。
-
 火葬場 火葬場
- 伊那市と長谷村にある火葬場の運営は、新市に引き継ぎ、民間委託を検討します。
- 火葬場使用料は、次のとおり統一します。
-
-
| | 市 民 | 市民以外 |
|---|
| 10歳以上 | 10,000円 | 50,000円 |
| 10歳未満 | 6,000円 | 30,000円 |
-
 イベント イベント
- 当面の間、現行のとおり実施し、既存のイベントを通じ、県内外からの観光客の誘致に積極的に取り組み、新市をPRしていきます。新市全体を捉えた一体的なイベントを企画していきます。また、合併後は地域の特色を活かしたイベントを企画するとともに統廃合を検討していきます。
-
 公営住宅 公営住宅
- 市町村営住宅は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に管理方法を調整します。
- 住宅使用料は、当面の間、現行のとおりとし、合併後に調整をします。
-
 道路除雪対策 道路除雪対策
- 主要道路の除雪作業は委託又は直営とし、その他の道路は地元の皆様との協働により行います。また、合併までに除雪マニュアルを策定します。(除雪対象路線については現行のとおりとします)
- 除雪機械の補助は、補助率50%、限度額50万円とします。
- 融雪剤は、地元自治会から要望があった場合に限り無料で配布します。
-
 道路整備 道路整備
- 受益者が特定される生活道路整備の受益者負担率は、事業費の5%とします。ただし、1戸あたりの受益者負担金には限度を設けます。
- 用地補償は、路線価等を参考にしてその都度決定します。その他の補償は県の基準に準じます。
-
 住民の交通福祉対策 住民の交通福祉対策
-
-
| 事務事業 | 対象者 |
調整結果 |
|---|
廃止路線代替バス運行
維持対策 | 一般市民 |
現行のとおり運行します。 |
| 循環バス運行事業 |
現行のとおり運行します。
・旧市町村間を結ぶ循環バスの運行については、合併
後速やかに運行できるよう関係機関と調整します。
・公共交通手段のない地区の交通対策については、新
たなデマンド交通 ※ を検討し、バス路線も含め効率
的で利用者の要望に沿った交通手段の確立を検討し
ます。 |
バス運行維持対策に
係る補助 | 観光客・
一般市民 |
・現行のとおりとします。
・権兵衛道路開通に伴い伊那と木曽を結ぶバス路線の
開設について検討します。 |
高齢者バス・タクシー
利用料金助成 | 健常高齢者 |
低所得高齢者が、原則として医療機関・公共施設等への通院、通所に利用するバス・タクシーの利用料金の一部を助成します。
1 交付対象者 次のすべての要件に該当する者
(1) 市内に在住する75歳以上で介護保険の所得段階
が1・2の者
(2) 移送サービス事業(車いす・ストレッチャー車によ
る移送)の対象者でない者
(3) 障害者等タクシー利用助成を受けていない者
2 助成額
バス主要駅までの距離により1人年額2,400円・4,800
円・7,200円・9,600円・12,000円を100円券で交付しま
す。 |
移送サービス事業
(外出支援サービス) | 高齢者、車椅子利用者、一般の交通手段を利用することが困難な者 |
寝たきり等のため、車いすやストレッチャーを使用しなければ外出が困難な人が、リフト付き自動車やストレッチャー車で市内及び隣接等の医療機関へ通院したときの移送料金の助成を行います。なお、現在、無料で送迎を実施している機能訓練等については、事業と関連して検討します。
1 助成の対象
福祉タクシー及び福祉有償運送
2 個人負担金
運賃の1/2の額とします。
ただし上限は1,000円とします。 |
寝たきり老人等通所通院
タクシー利用助成事業 | 寝たきり老人等 |
重度身体障害者移動
支援事業 | 重度身体
障害者 |
新市において福祉有償運送を実施する民間団体と調整していきます。 |
在宅重度心身障害者(児)
自動車燃料費補助 | 在宅重度心身障害者(児) |
新市に移行後も、実施するものとします。
対象者は伊那市の基準とし、年間2万円とします。
○対象者
・下肢・体幹機能障害1〜3級
・視覚・内部障害1級(人工透析を含む)
・知的障害者A1
・施設入所者・タクシー利用助成者は除く。 |
在宅重度心身障害者(児)
タクシー利用料助成事業 | 在宅重度心身障害者(児) |
対象者を伊那市の基準とし、年間2万円を限度にタクシー券を交付します。
(自動車燃料費補助若しくはタクシー利用助成のいずれか一方が対象となります) |
共同作業所等通所者
交通費補助 | 共同作業所等通所者 |
新市に移行後も実施するものとします。
補助金の額は通所のための交通費の1/2以内とし、最も近い施設を原則とします。
交通費の算出については以下のとおりとします。
○公共交通機関利用者
1月当たり交通単価×通所月数×1/2
○自家用車
距離単価×往復距離×通所日数×1/2
施行時期は新市発足時とします。 |
- ※利用者の要望に応じて運行ルート、時間などを対応させる方法。
|